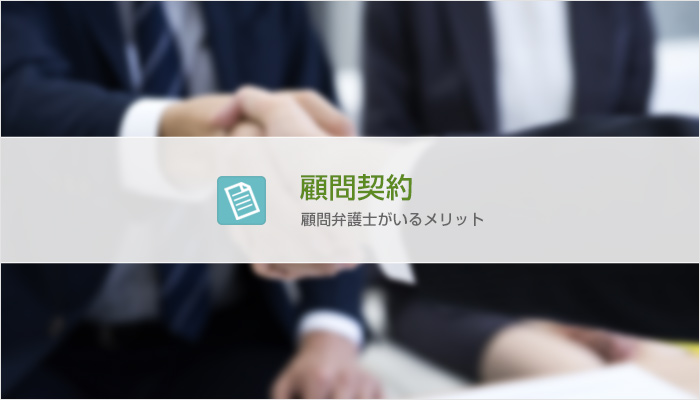
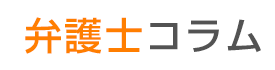
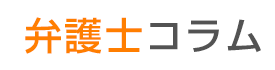
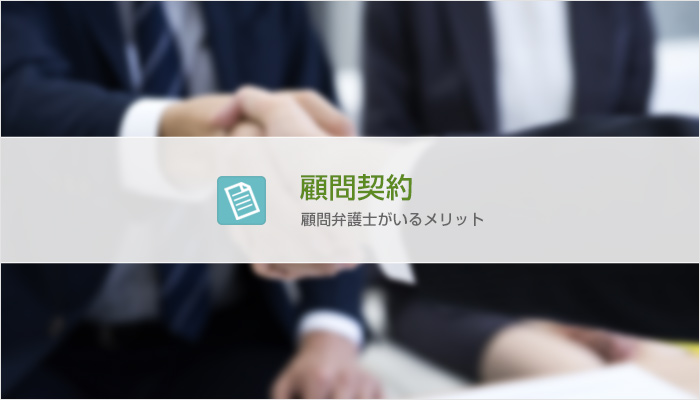
今回は定型約款についてお話します。
約款とは、不特定多数の相手と一律・定型的に取引をするための取引条項であり、現代社会では多くの場面で利用されています。
例えば、何かの会員カードを作ったときに、小さい字が大量に書かれた冊子を渡されたとしたら、そこに書いてあるのが約款です。
ほとんど誰も読んでいない約款について、今回の改正で初めて根拠規定が置かれました。
改正法は、「定型約款」に関して、以下のような定義をしています。
| 定型約款 | 定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体 |
|---|---|
| 定型取引 | ①ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、 ②その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの |
定型取引の典型例は、鉄道の運送や電気・ガスの供給、保険、インターネットサイトの利用などです。これらは、①利用者を選ばず、②画一的に契約内容が定まっていた方が利用者にとっても便利な取引です。
上記①の要件から、相手の個性に着目するような取引は対象外となります。たとえば、労働契約や賃貸借契約などは、通常は相手の能力や信用性に着目して契約します。したがって、たとえ同じ契約書を使いまわしていても、原則として定型取引に該当しません。
また、上記②の要件から、交渉が想定されるような取引は対象外となります。たとえば、フランチャイズ契約の多くは定型の契約書を使用しますが、これは交渉力格差の結果であって、交渉しないことが加盟店にとって合理的とは言いがたい面があります。そのため、これも原則として定型取引に該当しないとされています。
定型約款は、一定の要件を充たす場合、約款の個別条項について「合意をしたものとみなす」(合意擬制)とされています。
合意が擬制されると、「本当は合意していなかった」という反論ができなくなります。
定型約款について合意が擬制されるのは、以下のいずれかの場合です。
「定型約款を契約の内容とする旨」の合意又は事前表示があれば良いので、定型約款の内容自体は、認識も表示もする必要がありません。
つまり、「契約の内容は約款で」ということだけはっきりさせれば良いことになります。
しかし、読みもしない約款で一方的に不利な合意を擬制されてしまえば、悪徳商法の温床となってしまいます。
そこで、以下のような条項については、逆に「合意をしなかったものとみなす」として、不合意が擬制されています。
不合意が擬制されるので、実際には約款の内容をよく読み、不利を承知で合意したとしても、合意がなかったものと扱われます。
契約の内容にする以上、定型約款の内容を全く見せなくて良いわけではありません。
定型取引の前後で、相手方から請求があった場合には、遅滞なく定型約款の内容を示さなければなりません。
定型取引合意前の開示請求を拒否すると、合意が擬制されなくなります。
もっとも、定型約款の内容が記載された書面等(メールも可)を交付しておけば、この義務を免れることができます。契約時には、常に約款記載書面を交付しておく方が良いかもしれません。
以下のいずれかの場合には、個別の同意なく定型約款の内容を変更できます。
ただし、当事者間で「約款を変更しない」という合意がある場合は、上の要件を充たしても一方的には変更できません。
②の合理性判断では、変更の必要性や内容の相当性、発生する不利益の程度、不利益緩和措置の有無など、諸般の事情が考慮されることになります。
変更の際には、以下の要件を充たす必要があります。
周知の方法は、「インターネットの利用その他の適切な方法」とされています。
以上の約款に関する規定は、改正法施行日である2020年4月1日より前に締結されたものについても適用されます。
2018年4月1日から2020年3月31日までの間に、相手方に対し書面・メール等で反対の意思表示をすれば、締結済みの約款については改正法を適用させないことができます。
もっとも、改正前民法には約款の根拠規定がなく、法律関係が不安定となるおそれがあります。そこで、反対の意思表示をするかどうかについて、法務省は「十分に慎重な検討」を求めています。
弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市)では、中小企業の法律問題を中心に扱っております。
顧問に関する相談料金は無料ですので、お気軽にご相談ください。
顧問契約の形態・費用等は、貴社の事情により、相談に応じさせていただいております。
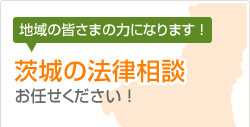
対応エリア
茨城県全域(石岡市、潮来市、稲敷市、牛久市、小美玉市、笠間市、鹿嶋市、かすみがうら市、神栖市、北茨城市、古河市、桜川市、下妻市、常総市、高萩市、筑西市、つくば市、つくばみらい市、土浦市、取手市、那珂市、行方市、坂東市、常陸太田市、常陸大宮市、日立市、ひたちなか市、鉾田市、水戸市、守谷市、結城市、龍ケ崎市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町)、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都など、関東地域
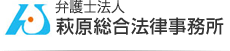
![]()