
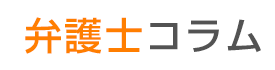
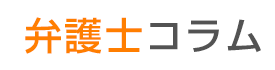

前回は「遺言の方式・手続 その1」として,①遺言の作成時には方式を守らなければならないこと,②その方式のうちの一つ「自筆証書遺言」の概略,③自筆証書遺言で必要になる「検認」の制度,④自筆証書遺言についての法改正と新制度をお伝えしました。
第2回の今回は,自筆証書遺言で問題になりがちな,守らなければいけない形式面の注意点についてお伝えしていきます。
この記事の目次
1 法律の規定
民法968条1項で,「自筆証書によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならない。」と定められています。
「全文」を「自書」つまり手書きすることになっています。もっとも,前回触れたように,自筆証書遺言と一体のものとして相続財産の目録を付ける場合,その目録については手書きでなくても許される旨の法改正がされています(同条2項)。
2 「自書」
繰り返しになりますが,原則的に手書きの必要があります。これは,他人の関与なく作れる自筆証書遺言では偽造・変造の危険性が高いためです。筆跡で本人が書いたことを判定し,本人の真意に基づくことを保障しようとしています。そのため,自筆性は厳格に判断されます。手の震えを他人に支えてもらいながら書いたものが,本人以外の意思が介入したとして無効とされた判例もあるほどです。
また,条文の文言からは「書」にする必要があるため,本人の言葉が録られた動画や音声データでも方式違反になります。そのため,映画でよく見かけるようなビデオメッセージでは民法上の遺言としての効力はありません。
逆に,何に書くか・何で書くかは定めがないので自由です。チラシの裏にクレヨンで書いても,他に形式違反がなければ法的な問題はありません。ただ,損傷や改ざんの危険性を考えると,長持ちする用紙に消せないペンで書くことが適切でしょう。
3 日付
作成した日付を書くことが必要です。二つの遺言が矛盾・抵触する場合,後の遺言で前の遺言の矛盾する部分を撤回したものと扱われるからです(民法1023条)。また,遺言する能力(内容は第5回で詳述する予定です)を遺言書の完成時に備えていたかが問題になった場合,いつ書いたものか明らかにする必要があることも理由です。
そのため,遺言書が完成した当日を年月日まで客観的に特定できないといけません。「〇月〇日」・「〇年〇月」だけだったり「〇年〇月吉日」とぼかしていたりすると方式違反で無効になります。「私の〇回目の誕生日」や「〇年の敬老の日」のような調べて日付が特定できる記述であれば有効ですが,気取らずに西暦または元号で年月日を書くことをお勧めします。
4 氏名
誰が書いたかを特定するために必要になります。
個人を特定できるならば,戸籍上の氏名に限らず,通称や芸名でも許されます。大正時代の判例では,他人と混同せず誰の遺言か分かる場合に,氏だけ・名だけでも有効と許したものさえあります。
個人の特定には有効な情報ですが,住所や生年月日まで書く必要はありません。
5 押印
自筆と合わせて遺言書が真意に基づいて作成されたことを担保するため,押印が必要です。自分の印章を使ってさえいれば自分の意思に基づくと示せるので,使う印章は実印に限られません。認印で構いませんし,判例では指印も許されています。なお,インク浸透印(スタンプ印)は,理屈の上では許されるはずですが,使わないように注意喚起する記述が法務局のパンフレットにあります。
また,押印は,作成者が署名・押印した段階で文書の完成として扱う日本の慣行から,完成を示すものとしても必要とされます。この趣旨に照らし,押印の習慣がない外国から帰化した方の場合に署名(サイン)だけで有効とした例があります。他方,花押(江戸時代頃まで流行していた署名代わりの手書き図柄)では,今の日本の慣行から外れているため,押印の代わりにはならず,有効な遺言とは認められません。
印を押す場所は,1通の遺言書といえる範囲で押されていれば足ります。複数枚組なら1枚に押してあれば足ります。封をした封筒の綴じ目に押してあれば本文の用紙に押印がなくても有効とした判例もあります。
加筆・削除・訂正にも,方式が定められています。遺言者が,その場所を示して変更した旨を付記し,署名し,変更の場所に印を押す必要があります(民法968条3項)。例えば,預金を相続させるつもりで「不動産を相続させる」と書いてしまったものを直す場合,「不動産」を取り消し線で消して印を押し,近くに「預金」と書き,「〇行目の『不動産』を『預金』に訂正した」と書いたうえで署名する必要があります。
意味が変わるような訂正が方式に沿っていない場合,訂正部分だけでなく,関係する文章全体が効力を失うこともあり得ます。上の例だと,不動産・預金についての指定だけでなく財産関係の記述全体が無効になる可能性もあります。
大きな訂正の場合,全体を書き直すことが安全でしょう。
今回は形式面での注意点をお伝えしました。説明の中で,かろうじて許された例をいくつかご紹介しましたが,危険なので真似はしないでください。
せっかく作成した遺言が形式の点で無効にならないように,作成に際して弁護士に相談することをお勧めします。
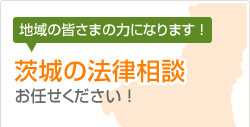
対応エリア
茨城県全域(石岡市、潮来市、稲敷市、牛久市、小美玉市、笠間市、鹿嶋市、かすみがうら市、神栖市、北茨城市、古河市、桜川市、下妻市、常総市、高萩市、筑西市、つくば市、つくばみらい市、土浦市、取手市、那珂市、行方市、坂東市、常陸太田市、常陸大宮市、日立市、ひたちなか市、鉾田市、水戸市、守谷市、結城市、龍ケ崎市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町)、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都など、関東地域
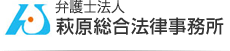
![]()