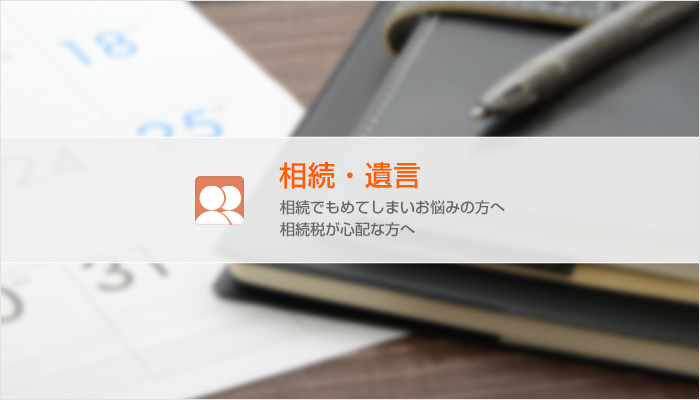
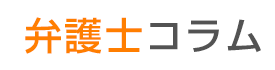
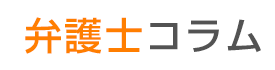
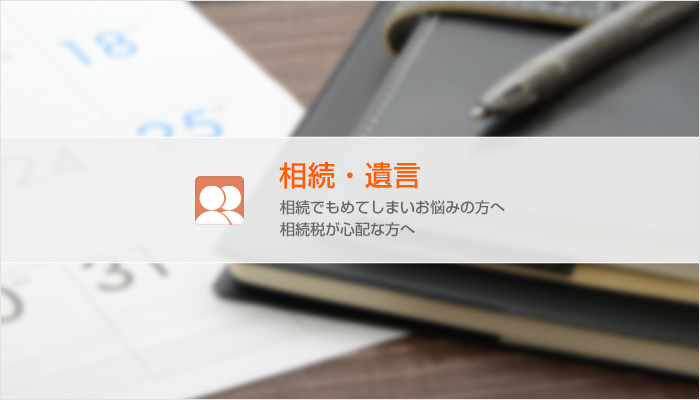
令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました(不動産登記法76条の2)。相続登記の申請義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります(不動産登記法164条)。
今回は、架空の事例を用いて、相続登記の申請義務化についてご紹介いたします。
| 【事例】
・Xは、令和元年3月に亡くなりました。Xと妻は既に離婚していたため、子であるY、Zの二人が相続人となりました。 ・Xは、X名義で登記されている甲土地、甲建物、乙土地を所有していました。また、Xは、乙土地上に未登記の乙建物も所有していました(古い建物を相続した場合など、事案によっては、建物としての登記が無い場合があります。)。Xの遺産は、これらの不動産のみでした。 ・Yは家族と疎遠だったため、Xの遺産の中にどんな財産があるか知りませんでした。しかし、令和元年4月に行われた葬儀の際、Yは、ZからXの遺産の内容を聞きました。 |
民法の改正により、①「所有権の登記名義人について相続の開始」があり、②「相続により所有権を取得した」相続人は、③「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました(不動産登記法76条の2第1項)。
本件では、相続登記の申請義務化の施行日である令和6年4月1日よりも前に、Xが亡くなっています。施行日前に相続が発生していれば、相続登記の申請義務を負わないでしょうか。
これについては、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記の申請義務化の対象となってしまいます。その場合、施行日(令和6年4月1日)から3年以内である令和9年3月31日までに登記申請が必要になります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。
1 本件では、誰が、どの不動産について相続登記の申請義務があるでしょうか。上記第1の①~③の要件をみていきます。
⑴ ①「所有権の登記名義人について相続の開始」があった
「所有権の登記名義人」とは、登記記録の「権利部」に権利者として記録されている者をいいます(不動産登記法第2条第11号)。しかし、未登記の建物は登記されていないことから「権利部」がありません。
そのため、甲土地、甲建物、乙土地はXが「登記名義人」ですが、乙建物には「登記名義人」がいません。
したがって、甲土地、甲建物、乙土地については①の要件をみたしますが、乙建物については①の要件をみたしません。
⑵ ②「相続により所有権を取得した」
本件で、被相続人Xの相続人はY、Zです。被相続人が亡くなった時点で、相続財産の不動産については、相続人同士で共有する状態(複数人で共同所有している状態)になります。相続人同士で共有する状態は、遺産分割協議等で解消することはできますが、まだ遺産分割協議をしていない今の時点では、YとZは、「相続により所有権を取得した」といえます。
⑶ ③「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った」
令和元年4月に行われたXの葬儀の場で、YとZは、X名義の財産について話し合いをしています。そのため、遅くとも令和元年4月時点で、YとZは自己のために相続が開始され、所有権を取得したことを知ったといえます。
2 以上より、YとZは、甲土地、甲建物、乙土地について相続登記の申請義務を負い、3年以内に相続登記をする必要があります。そして、乙建物については、未登記建物であることから相続登記の申請義務を負いません。
ただし、未登記建物については、「表題登記が無い建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。」と今回の改正以前から規定されています(不動産登記法47条)。
そのため、YとZは、乙建物について表題登記をする義務を負っています。
1 遺産分割協議が長引くなどして、3年以内に相続登記をすることができない場合、過料の対象になってしまうのでしょうか。
このような場合を想定し、相続人申告登記(不動産登記法76条の3)という制度も追加されました。
相続人申告登記は、①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官(不動産を管轄する法務局)に対して申し出ることで、申請義務を履行したものとみなされます。
相続人申告登記の場合は、共同相続人の1人から申出ができますし、代理で申出することもできます。また、相続登記と異なり、法定相続人の範囲や相続分の割合の確定は不要です。そのため、かなり簡略化された手続きといえます。
ただし、相続人申告登記をした後は、遺産分割が成立した場合に「遺産の分割の日から三年以内」に登記しなければならない義務が生じますので、3年の延長ということになります。最終的には、相続登記をしなければならないことに変わりはありません。
また、登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行した扱いになるにすぎません。他の相続人は相続登記の義務を負い続けていることに変わりはありませんので、注意が必要です。
2 本件でYとZは、仮に両者の間で遺産分割協議がうまく進まず、3年以内に相続登記ができないようであれば、相続人申告登記を行うことになります。そして、遺産分割協議が成立したら、遺産分割が成立した日から3年以内に、取得した対象不動産の相続登記をしなければなりません。
以上
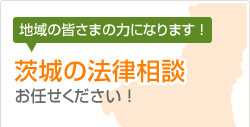
対応エリア
茨城県全域(石岡市、潮来市、稲敷市、牛久市、小美玉市、笠間市、鹿嶋市、かすみがうら市、神栖市、北茨城市、古河市、桜川市、下妻市、常総市、高萩市、筑西市、つくば市、つくばみらい市、土浦市、取手市、那珂市、行方市、坂東市、常陸太田市、常陸大宮市、日立市、ひたちなか市、鉾田市、水戸市、守谷市、結城市、龍ケ崎市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、河内町、八千代町、五霞町、境町、利根町)、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都など、関東地域
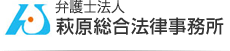
![]()